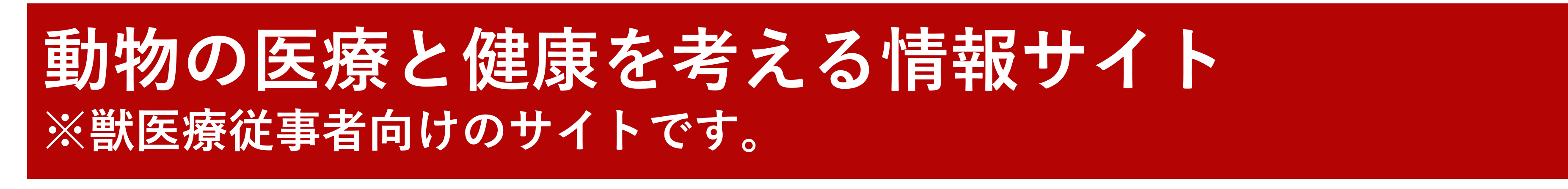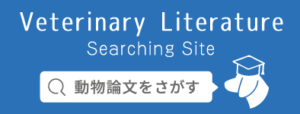黄色い“シロ”さん
気が強いネコのシロさんは、以前、家庭でご家族と仲良くできなかったそうです。
勝手に住み着いたので年齢不詳ですが、推定12−3歳くらいです。
病気になって何かを悟ったのかわかりませんが、性格が丸くなって「触れるようになりました」とのこと。しかし来院時、丸くなっていたのは性格だけではありませんでした。
お腹も丸い。腹水とすごい脾腫でした。
初診時のビリルビンは22mg/dL。耳などは真っ黄色です。
シロさんの病状と治療
そんな黄色い“シロ”さんの肝酵素データは、ALTが1000IU/L以上で、貧血もHt23.7%と結構シビアです。黄疸の原因をさぐるため、さっそく超音波検査を行なってみましたが、肝臓実質が全体的に汚い。胆管壁が肥厚、しかし胆管閉塞はなさそうでした(図1)。きっと肝性黄疸です。
.png)
図1.腹部超音波画像
シロさんの腹部超音波像。左は層構造がみえるようになってしまっている胆嚢。肥厚しています。
右は胆嚢から胆管を追ったところ。胆管も著しく肥厚しています。
そして腹水に加え、かなりの脾腫。
オーナーさまはドクターでしたので、データをみていただき病状をありのまま説明しました。
結論として、特に積極的な検査(肝生検とか)や治療を行わず対症療法でいこうということになりました。この肝酵素値では、なかなか厳しいかな、と思っていました。
ここからシロさん、がんばります!
とりあえず化膿性の胆管管炎なら抗菌薬が奏功するかも、と思い、肝臓排泄の抗菌薬としてドキシサイクリンを処方させてもらいました。偶然ですが、これがよかったようです。
なんと貧血が改善。エリスロポエチン製剤も少し使わせてもらいましたが、抗菌薬の効果はすばらしくHt40%くらいをキープできるようになりました。血液塗抹では見つけられなかったのですが、たぶんヘモプラズマがいたということですね。ラッキーでした。