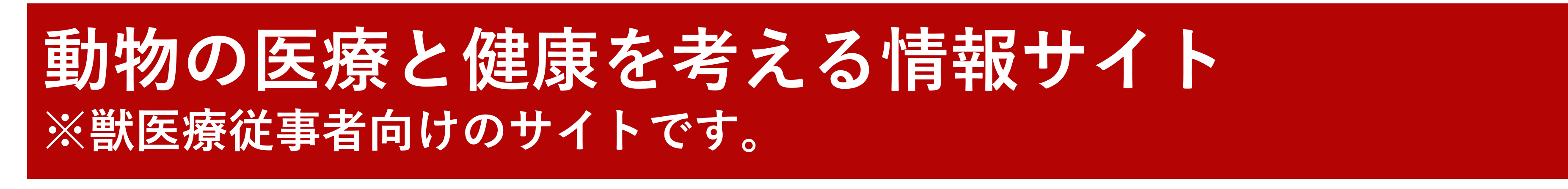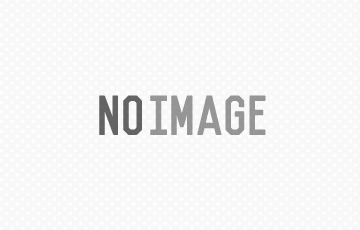ネコにおける膵炎は、その多くが慢性膵炎で急性膵炎は少ないとされています。さらに、術後急性膵炎を起こすことは非常に稀です。しかし、開腹手術ではない術式で急性膵炎が発症したという報告があったため、論文をご紹介します。
症例
症例は、右前肢の滑膜肉腫の治療のために断脚術を実施した、14歳齢の長毛雑種避妊雌です。術後に急性膵炎と診断されました。
経過
手術中は血圧・心拍数・呼吸状態などのモニター項目に異常は認められず、麻酔時間は約120分、手術時間は約50分で、麻酔からの覚醒もスムーズに進み、周術期において特に問題はありませんでした。また、術後6時間までの尿量のモニターも2~3 mL/kg/hと正常範囲内でした。
手術翌日の血液検査では、手術侵襲によるSAAの上昇と、軽度の低カリウム血症が認められましたが、低カリウム血症に関しては点滴で補正をし、術後2日間は食欲正常、一般状態も良好でした。
しかし、術後3日目に突然食欲が廃絶、全身状態が悪化し、血液検査で好中球減少(1,110/μL)を主体とした、白血球減少症(1,790/μL)が認められたため、処置として30 mLの鮮血の輸血と、顆粒球コロニー刺激因子を投与しました。
翌日、白血球は上昇に転じましたが、軽度の高窒素血症と、血清総ビリルビン濃度の上昇が認められたため、輸液治療とウルソの投薬を行いました。処置により高窒素血症は改善したものの、7病日目に血清総ビリルビン濃度は5.0 mg/dLにまで上昇し、黄疸を示しました。
そのため、腹部超音波検査を実施したところ、厚さ8.3cmに腫脹した低エコー源性の膵臓と、周りの脂肪組織が高エコー源性となった所見が認められたため膵炎を疑い、さらにネコ膵特異的リパーゼの定性検査で強陽性を示したことから、術後急性膵炎と診断しました。
膵蛋白分解酵素阻害剤 と抗生剤、輸液療法、経腸栄養補給といった、急性膵炎に対する内科的治療を実施した結果、血液検査所見と全身状態は改善しました。初診から8カ月が経過した現在も全身状態は良好です。
考察
これまで、膵臓生検や副腎摘出術など、腹腔内手術後においての術後急性膵炎の報告はいくつかあり、腹腔手術による直接的あるいは間接的な刺激が要因と考えられていました。
しかし、今回の症例により、腹腔内操作を行っていない手術後においても、急性膵炎が発生する可能性が示唆されました。今回の症例において術後中のモニターは安定しており、膵炎の要因となる薬剤の使用や、感染症の病歴なども一切ありませんでした。
そのため、術後に白血球減少が認められたこともあり、全身性炎症反応症候群(SIRS)あるいは、播種性血管内凝固(DIC)が要因とも考えられましたが、術後のモニターが正常なことからSIRSは否定的でした。
一方、術後の臨床症状の悪化に伴い、血小板の軽度減少が認められたことから、悪性腫瘍に対する侵襲的手術を行った本症例において、急性膵炎に先行したDICにより、膵臓に微小血栓ができ、急性膵炎を生じた可能性は否定できません。
まとめ
ネコの急性膵炎の約15%で、初期症状として白血球減少症が認められることが明らかになっています。今回の論文でも、症例に白血球減少症が認められました。また、手術後に白血球減少が認められるネコにおいては、炎症性疾患やSIRS、DICを念頭におきながら、適切な検査や治療を行うことが求められるでしょう。
獣医師J
【参考文献】
板本拓也, 根本有希, 伊藤晴倫, 砂原央, 堀切園裕, 井芹俊恵, 板本和仁, 谷健二, 中市統三, 白血球減少症を伴った術後急性膵炎の猫の1例,日本獣医麻酔外科学雑誌,2021,52 巻,2 号,p.31-35,
【関連製品】
膵特異的リパーゼが定量で測定可能!

【関連記事】