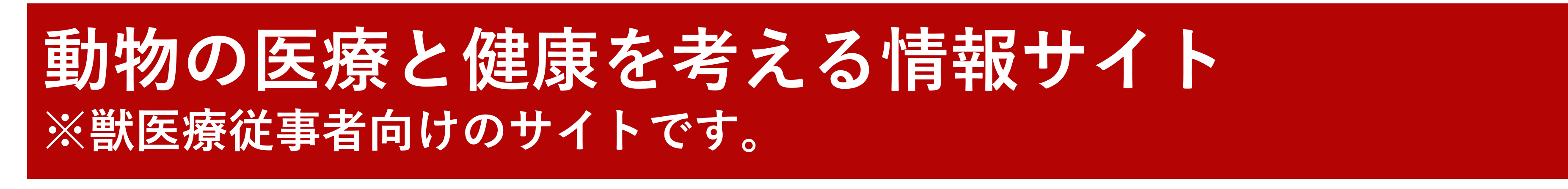血液検査でカルシウム値が基準よりやや高めに出た際も、そのほかの症状がない場合には、経過観察でよいと判断されがちです。しかし、軽度高カルシウム血症は、重篤な疾患の早期兆候の場合もあるため、慎重な評価が必要です。そこでこの記事では、文献をもとに軽度高カルシウム血症の診断と管理のポイントについて解説します。
高カルシウム血症とは
高カルシウム血症とは、血清中のカルシウム濃度が基準値(検査機器などによっても異なるがおよそ8.0 〜12.0 mg/dL)を超えている状態です。明らかな高カルシウム血症では、脱水、食欲不振、嘔吐、便秘、筋力低下、多飲多尿などが現れますが、軽度の場合は無症状であることが多く、見逃されがちです。
軽度高カルシウム血症とは
一般に総カルシウム値が11.9 〜12.5 mg/dL程度の軽度上昇や、イオン化カルシウム(iCa)が1.4〜1.5 mmol/L程度の境界域は、「経過観察でよい」と判断されることが少なくありません。しかし、これは副甲状腺機能亢進症や腫瘍性疾患(特にリンパ腫や肛門嚢アポクリン腺癌)などの早期兆候の可能性もあり、注意が必要です。
診断アプローチと評価のポイント
軽度の高カルシウム血症が認められた場合には、以下のアプローチが推奨されます。
・イオン化カルシウム(iCa)の測定
総Caだけではなく、実際に生理活性を持つiCaを測定することで、臨床的な意義が明確になります。
iCaは、主に血液ガス分析装置で測定可能です。
・原因精査のためのホルモン測定
副甲状腺ホルモン(PTH)や、副甲状腺ホルモン関連タンパク(PTHrP)などの測定を組み合わせることで、原発性副甲状腺機能亢進症や腫瘍随伴症候群の鑑別が可能になります。
・慢性腎臓病との関連評価
腎機能障害が進行すると、リンやカルシウム代謝の異常が起こることがあります。SDMAや尿検査を組み合わせた、腎機能の評価も同時に行うとよいでしょう。
・再検査と経過観察
軽度高カルシウム血症が一過性なのか持続性なのかを判断するには、数週間以内の再検査が有用です。健康診断の一環として見つかることが多いため、定期的なモニタリングが診断の鍵となるでしょう。
―――――――――
<PR>いつもの尿検査でUPCも測定
尿化学分析装置 thinka RT-4010
―――――――――
まとめ
軽度高カルシウム血症は、無症状であってもさまざまな疾患の前兆である可能性を含んでいます。特に早期の腫瘍性疾患や内分泌疾患を見逃さないためには、iCaの測定やホルモン評価、再検査による追跡が重要です。年1回の健康診断の数値を見逃さず、しっかりと精査することで、疾患の早期発見・早期治療につなげましょう。
獣医師G
【参考文献】
Peterson ME. “Evaluation of Mild Hypercalcemia in Dogs and Cats.” Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 2023.
【関連記事】