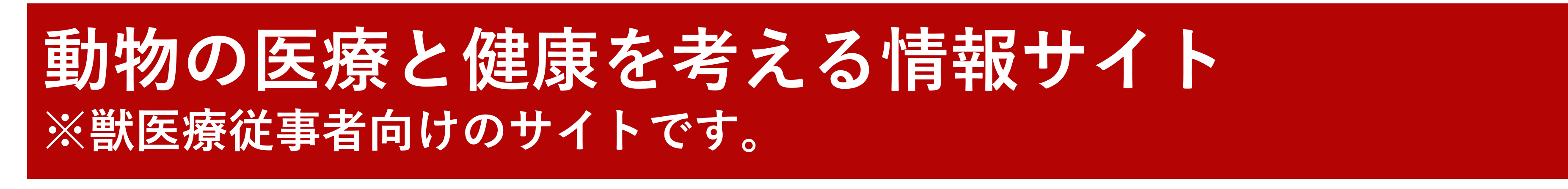この記事では「イヌ・ネコにおける術前希釈式自己血採血・輸血の安全性と可能性について」という論文の内容を、獣医師である筆者が要約としてまとめました。最新の論文に目を通し、業務にお役立てください。
輸血における現状
日本の獣医療における血液供給体制は未成熟で、慢性的に血液製剤が不足しています。また、最も一般的な輸血方法「同種血輸血」は、輸血副作用のリスク・保存血液の機能低下・血液バンクの組織と維持に伴うコストなどが課題と言われています。特に、同種血輸血の副作用は軽度の発熱から、生命を脅かす溶血性反応までさまざまで、イヌでは症例の3.3~37.4%で、ネコでは8.7~12%も認められるため注意が必要です。
希釈式自己血輸血について
待機手術を控えた症例自身の血液を採取・保存し、周術期に症例に投与する方法が「自己血輸血」です。自己血輸血は同種血輸血と比較し、副作用が少なく、入院期間を短縮できるのがメリットとされています。
自己血輸血のなかでも、手術日の麻酔導入後に採血し、採血後に採血量と同量の膠質液を静脈内に急速投与して循環血液量を確保する方法が「希釈式自己血輸血」です。輸液により血液が希釈されることから、希釈式と呼ばれています。
希釈式自己血輸血のメリットは、症例の血液が薄まるため、手術中の実質的出血量を減少できる、返血(希釈式自己血輸血を実施)される自己血が新鮮血であるため、血小板機能や凝集因子が保持できることなどです。
一方、デメリットは、採血により麻酔時間が延長すること、代用血漿投与過剰により血小板付着能の低下、フィブリン形成の異常、凝固因子の希釈効果による出血傾向が発生しやすくなることなどが挙げられます。そのため、心不全や腎機能障害があり、血液希釈に対しての生理学的代償作用が発揮できない症例や止血異常がみられる症例は原則、適応外です。
対象のイヌ・ネコと輸血方法
対象となった症例はイヌ40頭、ネコ2頭です。犬種はさまざまで、ネコはスコティッシュフォールド とソマリでした。イヌの年齢の中央値は11歳(範囲:5~15歳)で、血液型はDEA1.1陽性が39頭と、陰性が1頭でした。また、ネコは9歳と10歳で、どちらもA型でした。
症例の手術内容は全頭が何らかの開腹手術であり、副腎腫瘤切除の症例のなかには腫瘍栓が後大静脈内に伸展している症例が2頭いました。
イヌ・ネコ共に10~15 mL/kg を目安に採血し、日本自己血輸血学会のガイドラインを基に作成したプロトコル通りに全量を自己血採血後6時間以内に投与しました。
自己血輸血の結果
症例のイヌ40頭、ネコ2頭のうち、実際に術中または術後に、自己血の返血を必要としたのはイヌ33頭、ネコ2頭でした。採血時には18頭で一過性の低血圧がみられましたが、膠質液の投与により改善し、手術の延期や合併症は認められませんでした。また今回、返血した全症例で輸血関連合併症は認められませんでした。
ただ、42頭中1頭が周術期に、肝臓手術時の多量出血が原因で死亡。その他の41頭は、術後2~15日目に安定した状態で退院することができました。
考察とまとめ
今回、希釈式自己血輸血を行った全症例で、輸血関連合併症は認められませんでした。一方で、希釈式自己血輸血を実施した症例のなかで術中死が1頭でみられたため、血液希釈に伴う凝固因子の希釈による止血異常は慎重に考慮すべき点と考えられました。
これにより、希釈式自己血輸血は重度な貧血や心疾患が無く、想定される低血圧への準備があれば、イヌ・ネコへの安全性は高く、希釈式自己血輸血は同種血輸血に代わる実行可能な方法として検討すべきと言えるでしょう。
獣医師D
【参考文献】
Taisuke IWATA, Lisako TAKAHASHI, et al. Safety and Feasibility of Preoperative Hemodilutional Autologous Blood Donation and Transfusion in Dogs and Cats. Japanese Journal of Veterinary Anesthesia & Surgery, 2022, Vol.53. 2. 17-23.
【関連記事】